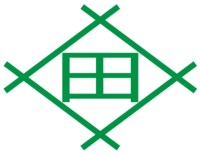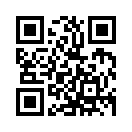Tange industry, the diary of the representative.
田家工業 代表 田家英雄の日記
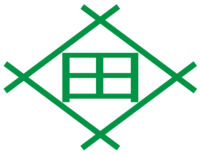
令和8年2月
2月になりました。 立春とは名ばかりで、関東では一年で最も冷え込みが厳しい時期を迎えています。 暖冬とかと思っていた時期もありましたが、冬本番です。身に染みるような寒気が続いております。
昨年もこの時期に、フキノトウの「苦味」について触れました。 子供の頃は遠ざけていたあの苦味が、経験を重ねるごとに「旨み」へと変わる。これは、現場で汗を流し、時には厳しい局面を乗り越えてきた我々建設業界の人間には、どこか通じるものがあると感じます。 仕事も人生も、甘いことばかりではありません。むしろ、苦い経験や辛い時期をどう「隠し味」に変えていくか。そこに、その人の、あるいは組織の「人間力」が表れるのではないでしょうか。
最近の社会を見渡すと、さらに加速するDX化やAIの活用により、あらゆる物事が「簡素化・効率化」されています。もちろん、危険な作業を減らし、生産性を高めることは我々の業界でも不可欠です。しかし、便利さを追求する一方で、大切な何かが削ぎ落とされているような危惧も拭えません。
「誰一人取り残さない社会の実現」
美しい響きの言葉ですが、実社会を見渡すと、効率化や合理化の名のもとに、多くの「声なき声」が切り捨てられているように感じてなりません。 システムを新しくすること(DX化)が目的になり、その先にある「人」が見えなくなっていないか。操作ができる人だけを基準にして、そうでない人を置き去りにしていないか。
言葉だけが独り歩きし、血の通った配慮が置き去りにされている現状に、強い危機感を覚えます。
言葉には「言霊」が宿ります。 立場ある者が発する言葉は、スローガンであってはなりません。それは覚悟であり、約束です。 私たちは、最新の技術を取り入れつつも、技術が人間力を追い越してしまわないよう、常に自らの心を省みる姿勢を忘れてはならないと考えます。
我々が扱う鉄骨は、建物の「骨組み」です。見えないところで全体を支え、何十年もその場所で耐え続ける。そこには、数値化できない職人の勘や、現場での細やかな意思疎通、そして「安易な妥協を許さない」という責任感が宿っています。 効率という物差しだけで測れない、この「手間」や「愚直さ」を排除してしまえば、結局は脆い社会になってしまう。私はそう考えます。
春は近づいていますが、もう少し寒風の厳しさが続きます。 簡素化していいもの、決して簡素化してはいけないもの。 その見極めをしっかり行い、何より現場で一生懸命に働く社員一人ひとりの心に寄り添いながら、「利他の心」を持って、無事故・無災害を徹底して有意注意で作業に取組み、社員との報連相は密にとり、技術だけが先行し人間力が置いてきぼりにならないように利他の心をもって精進して参ります。
最後になりますが、今なお困難な状況にある被災地の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と、一日も早い復興をお祈りしております。
この度は、弊社ホームページをご覧いただき大変ありがとうございます。
お問合せはこちら
茨城町の株式会社田家工業のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが…
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。